![Ken Yokoyama New Single [These Magic Words] リリース特設サイト](./assets/img/mv-img.png)
![Ken Yokoyama New Single [These Magic Words] ジャケット画像](./assets/img/release-jkt.jpg)
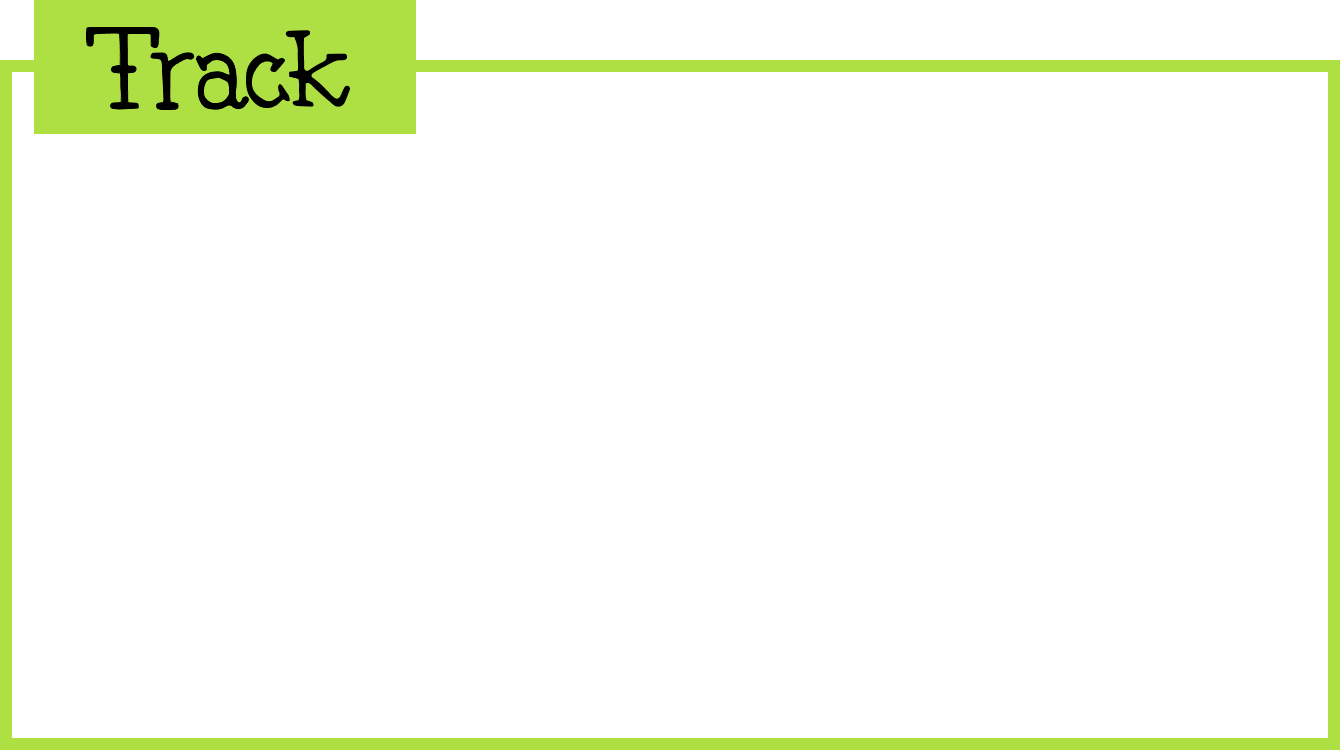
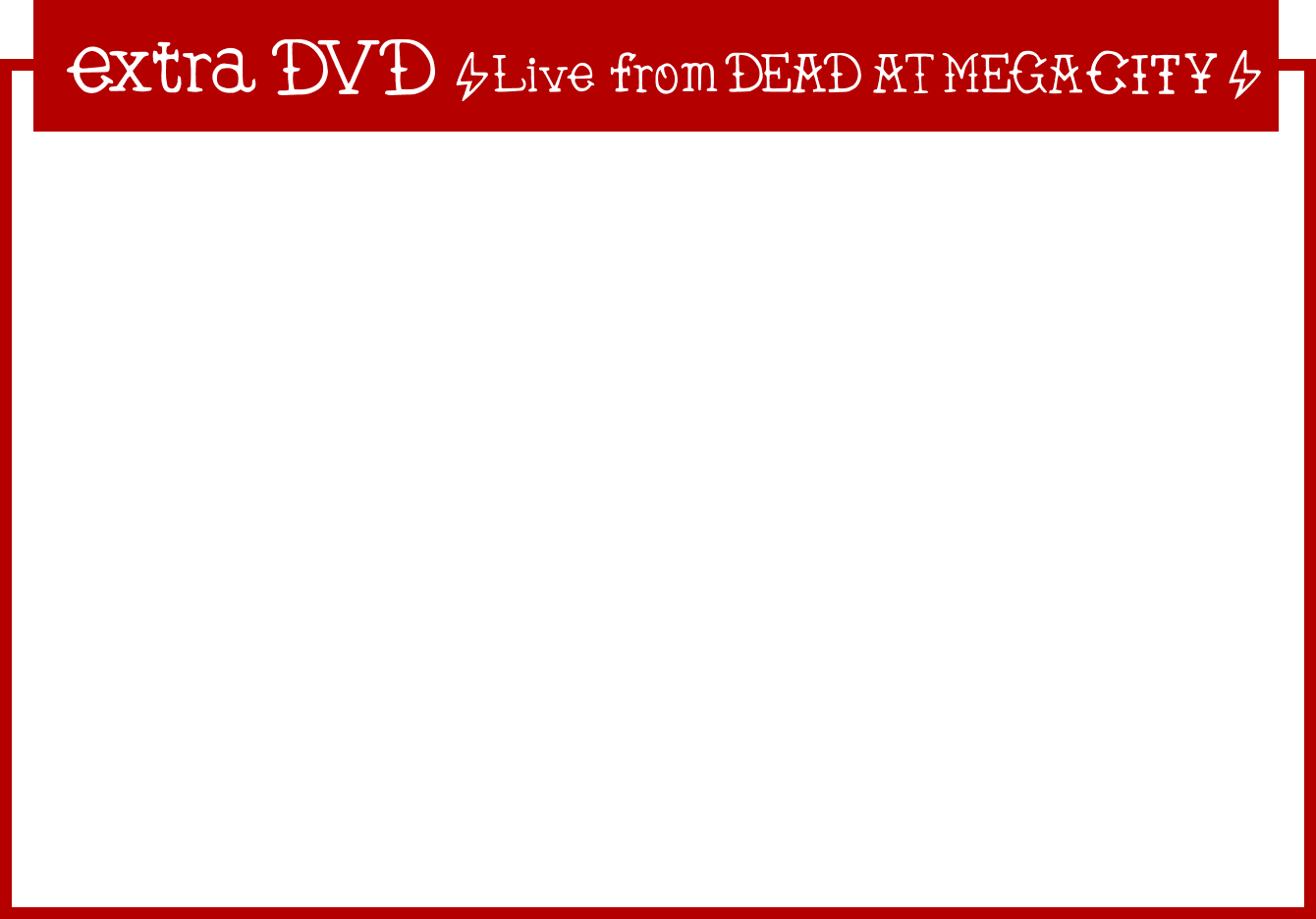
(日)岐阜Club Roots
(火)静岡浜松 窓枠
(水)静岡SOUND SHOWER ark 清水
(金)神奈川横浜 Bay Hall
Interview Vol.01
―― 現在、初めてのホールツアー「My One Wish Tour」の真っ最中ですが、名古屋と大阪公演を終えた手応えから聞かせてください(取材は10月下旬に実施)。
KEN 個人的には、ホールツアーがこんなに快適なものだとは思ってなかったですね。ホールでのライブはコロナ禍の最中からイベントとかでやってたし、オールスタンディングでも「動かないでね」ってほぼホールと近い条件のライブもやってたんですけど、やらざるを得ないそれと、自分達で選択するそれ。しかも今はお客さんが声を出せる。すごくいい空間なんだなというのを実感しています。
Jun-Gray ホールじゃないけど、その前に日比谷野音でやってますからね。声は出せるけど、席は決まっているという意味で、今(のホールツアー)と近かったと思うんですよ。ただ、野音の時は、俺なんかはぶっちゃけちょっと戸惑ったところがなくはなかったんですよ。いくら声が出せるって言っても、モッシュやダイブありの以前見てた光景とはやっぱり違うから。でも、ライブをやっている最中にもう、あ、こういう感じなのね。これはこれでおもしろいじゃんって感覚はあったから、名古屋と大阪も……あ、でも、やっぱりちょっと思ったかな。名古屋公演の前、ライブハウスも回ってたんですよ。そこからの名古屋だったから、正直、1曲目、2曲目ぐらいは、あ、そうだ。これはホールなんだって思うところはありました。お客さんのリアクションは当たり前ですけど、ぐしゃっとならないわけだから。そういうのはあったけど、でも、すぐに、これはこれでおもしろいって思えました。やっぱりぐしゃっとなるライブハウスでは味わえないような、お客さんとのコミュニケーションがあるような気がします。ライブハウスだと、いかつい奴らが前を埋めてるから、当然、荒っぽいコミュニケーションになるじゃないですか。でも、ホールだと、ライブハウスでは後ろのほうで大人見している人も最前列にいたりして、そういう人達とライブをやっていくってところもあるからおもしろいですよ。
―― セットリストはホールであることを意識して作っているんですか?
KEN そうです。大枠は変わらないですけど、ライブハウスでやると休憩時間になっちゃう曲があるんですね。やっぱり僕達、速いバンドなので、ミッドテンポの曲はそうなりがちなんですよ。正直、ミッドテンポの曲を作ったり、レコーディングしたりしているとき、「でも、ライブだと休憩時間になるよね」って意識がバンド内に芽生えてしまうほどイヤな問題だったんですけど、そういう曲がしっかりとできる。よそのバンドからしたら当たり前のことなんですけど、僕ら、今、それができている。それがすごくうれしいです(笑)。
―― そこで改めてミッドテンポの曲の魅力に気づくお客さんもいるんじゃないでしょうか。ところでツアータイトルになっている「My One Wish」はもちろんやっていると思うんですけど、カップリングの「Time Waits For No One」もやっているんですか?
KEN やってないんですよ。いや、「Time Waits For No One」はライブハウス向けだと思うんですよね。ホールでやるテンションの曲ではないんじゃないかって。
―― なるほど。そう言えば、この間、「Time Waits For No One」のコーラスは、ローリング・ストーンズの「Brown Sugar」を意識したとおっしゃっていましたが、ストーンズにも「Time Waits For No One」というタイトルの曲があったんですね。
KEN え、ありましたっけ。
―― すっかり忘れていましたけど、『It’s Only Rock’n’ Roll』に入っているんですよ。
KEN へぇ~。
―― Junさんもストーンズはけっこう聴いているんですか?
Jun-Gray 好きですよ。ロックを聴き始めたのは中1か中2の時なんですけど、きっかけは同級生から薦められたストーンズなんですよ。その1年後にはどっぷりパンクにハマるんですけど。
KEN 最初は何のアルバムだったの?
Jun-Gray えっとね、ジャケが変な形のベスト盤があったじゃないですか。『Through the Past Darkly: Big Hits 2』ってタイトルの。
―― ありましたありました。ジャケが八角形の。
Jun-Gray それを貸してもらったんですよ。だから、その頃から聴いてるし、その後もアルバムが出れば、買ってるし。今回のニューアルバム『Hackney Diamonds』も買って、聴いたばかりだし。けっこう好きですね。
―― 新作、意外に良かったですね。
Jun-Gray そうですね。
KEN 良かったですね。僕も聴きました。
Jun-Gray 70年代から80年代のストーンズの良さがありますよね。たぶんアンドリュー・ワットってプロデューサーの力がでかいんだろうなって俺は思います。
―― アンドリュー・ワットのプロデュースだったんですか。
Jun-Gray 今年の1月に出たイギー・ポップの『Every Loser』もアンドリュー・ワットがプロデュースしていて。
―― あ、そうでした。
Jun-Gray あれもイギーが一番活きが良かった70年代、80年代くらいの音を引き出していたと思うんですけど、そういうことをストーンズでもやっているんじゃないですか。一番輝いてた頃のストーンズを持ってきている。
KEN 中期ストーンズの感じがしますよね。ミック・テイラーがいた頃のストーンズの楽曲に近いものがある。
Jun-Gray PVになっている「Angry」って曲はそれっぽかったけど、アルバムになっちゃうとどうなんのかなと思いながら聴いてみたら、全体的にそういう感じなのねって(笑)。
―― すみません、話が脱線してしまいました。「Time Waits For No One」をやっていないということは、初回盤のみ付属のExtra Discに収録されていたJunさんボーカルの「Fuck Up, Fuck Up」もやっていないんですよね?
KEN 1回やりました。
Jun-Gray やったんですよ。大阪で。リクエストのコーナーがあって、誰もリクエストしてないのにKENが「歌え」って言い出して。
KEN ハハハ。
Jun-Gray 誰もリクエストしてねえのに歌うのかよってやったんですよ。
―― でも、ホールで歌うのは気持ちよかったんじゃないですか?
Jun-Gray いや、歌うこと自体苦手なんで、マジかよ。こんな大きなところで歌わせるなよってところはありましたけど。
KEN お客さんは歓んでました。
Jun-Gray やる時はやりますよ。
KEN ハハハ。
―― さて、ホールツアーも11月9日の東京公演を残すのみとなりましたが、東京公演ではひょっとしたらサプライズゲストも考えているんですか?
KEN (木村)カエラのことですよね?
―― そうです。木村さんを迎えて、「Tomorrow」をやるんじゃないかって期待している人は少なくないんじゃないかなと思います。
KEN いやー、結局、声を掛けられずにここまで来てしまいました。やっぱり、ちょっと気を遣ってしまうんですよね。新曲を出したばかりだから忙しいんだろうなとか思っちゃうんですよ(笑)。
―― 9月の中津川THE SOLAR BUDOKANで奥田民生さんのセッションに木村さんも出演されていましたけど、誰よりもノリノリでしたよ。
KEN 民生さんですからね。楽しかったと思いますよ。でも、僕ね、ホールでカエラとやりたくないと思ったんですよ。やるんだったらライブハウスに呼びたい。僕ら独特の、あのぐちゃぐちゃな感じは、まだカエラもステージ上からは体験したことないだろうから。だって、ホールは絶対慣れてるじゃないですか。
―― そうですね。
KEN それもあって、今回じゃないかなっていうのはありました。
―― では、いつかそのうちライブハウスでぜひ。さて、ホールツアーが終わって3週間後にシングルシリーズの最終章となる『These Magic Words』がリリースされるわけですが、今回もまた、それぞれに違う魅力を持った3曲が収録されています。前の2枚のシングル同様に円熟味とともに一皮剝けたソングライター=横山健を僕は感じたのですが、Junさんは今回のシングルの曲作りとか、バンドサウンドとかについて、どんなふうに捉えていますか?
Jun-Gray 前回のインタビューでも言ったとおり、今回の3曲も前の2枚のシングルと同じように今年の2月に録って、録ってからどういうふうに振り分けるか考えたんですけど、「These Magic Words」に関しては、たぶんKENが持ってきた段階で、「これは行けるでしょ」って手ごたえがあったんじゃなかったかな。逆に「My One Wish」はKENが持ってきた時は、そういう感じじゃなくて、「これ、行けるかな? まぁ、行けるんじゃね」って感じでアレンジしていってどんどん良くなっていったんです。でも、「These Magic Words」は最初から、「これは行ける」って雰囲気があって、うちらの中でもなんとなくだけど、シングルシリーズの最後を飾る曲になるんじゃないかっていう予感はあったと思います。
―― 今、お話を聞きながら、「My One Wish」が最初、それほどだったと聞いて、意外でした。
KEN 僕がそういう感じだったんです。「曲にはなるけど、いい曲に伸びるかどうかはわからない。とりあえずやってみよう」って感じで。でも、「These Magic Words」の時は、「もう、これ、いい曲を作ってきたから」っていう感じでした。
―― そもそもの話ですみません。横山さんがバンドに曲を持ってくる時って、どういう形で持ってくるんですか? デモトラックを作るんですか?
Jun-Gray デモはないですね。
―― じゃあ、弾き語り?
KEN 自分の記憶用にiPhoneに弾き語りを録っておいて、それをそのままメンバーに聴かせる時もあるし、スタジオで「こういうの作ったんだけど」って弾き語りする時もあるし、もう曲の断片からですね。
Jun-Gray ギター1本で、鼻歌で聴かせるみたいなね。その段階でAメロ、サビって曲の構成がちゃんと仕上がっているものもあれば、Aだけとか、サビだけとかで終わっているもものもあって。「These Magic Words」はAメロ、サビが全部セットで最初からあったのかな。
KEN サビから当然できたけど、どうだったかな。忘れちゃった。
Jun-Gray あったような気がするな。「My One Wish」は最初、全部揃ってなかったんですよ。
KEN サビだけあって、1回それだけバンドで録って。
Jun-Gray そこから段々広げていったんです。
KEN 練習の度に「こういうの思いついた」「こういうの思いついた」「これをイントロにすればいいんじゃないか」って。「These Magic Words」はもしかしたら全部あったかもしれないです。
Jun-Gray 曲の頭からサビまであって、そこから「2番はどうするんだ」「構成はどうするんだ」って。
KEN そうだそうだ。歌とギターから始まって、「ここでバンドがバーンと入って」「これがサビで」みたいに作っていったんだ。
―― 弾き語りから始まるというイメージは最初からあったわけですね?
KEN ありました。
Jun-Gray そこから広げていって、2番は早速転調しちゃおうぜって。
KEN そのまま歌うと、2番のキーが低そうで、なんとか転調して、歌いやすくできないかなって。そういう細かいことを1回録ったやつを聴きながらやっていきましたね。だから、すごくトリッキーな転調が入っているんです。要するに、この曲、Aメロとサビしかないんですけど、1番のAメロと2番のAメロのキーが違うんです。だから、Aメロに関しては、同じキーで歌うパートは2度と出てこない。
―― アルバムの制作を視野に入れていたと思うんですけど、アルバム全体のバランスを考えながら、「These Magic Words」は、どんな曲を作ろうと考えていたんですか?
KEN そういう目線では考えてなかったです。曲を思いついた時から、これはいい曲になると思ったので、かっこよく言うと、素材が求める通りに進めていきました。たとえそれがちょっぱやになろうが、ミドルテンポになろうが、これを生かすのにふさわしい速さと、それに合ったアレンジを付けてというふうに考えていきました。
―― Junさんのベースフレーズが1曲通してずっと動いているところも聴きどころではないかと思います。
KEN 全部、僕が「こうやってやって」と言うとおりやってくれるんで。
Jun-Gray うるせえよ(笑)。
KEN よくやってると思います(笑)。
Jun-Gray 何でも自分の物にしたがるな。
KEN ハハハ。
―― フレーズに関して、Junさんは割と動きたがりなんですか?
Jun-Gray 動きたがりですね(笑)。でも、それもあるけど、KEN BANDはギターが2人いますからね。ギターが1人しかいないバンドだとまた変わってくるんですけど、ウチらは1人が大抵、ストロークでコード感を出してくれるから、そうするとベースはルート音から外れていっても良いかな?とね。ライブもそうなんですけど。
KEN それ、間違えてるんじゃなくて?
Jun-Gray 間違えてる時もある(笑)。
KEN ハハハ。
Jun-Gray ライブはね。そういう意味でも自由に動ける部分がけっこうあるんですよ。ちょっと話が脱線しますけど、この間、ディセンデンツと一緒にやったんですけど、あのバンドはギターが1人しかいないのでレコーディングした音源を聴いていても、カール(・アルヴァレス)ってベーシストはテクニシャンだし個性的で凄いと思うけど自由にルート音を外れていくから危なっかしいなと思うところがあるんですよ。こんなにルートから外れていっていいのかなって。でも、そういう点でもKEN BANDはMinamiちゃんがしっかりストロークで弾いてくれてるから、けっこうフレーズで遊べますね。
―― 「These Magic Words」のベースライン、かっこいいと思います。
KEN ありがとうございます。僕が考えました。
Jun-Gray ふざけんなよ。
KEN ハハハ。
Jun-Gray サビの中でギターのね、よく言うと、シャレオツなコードなんだけど、ちょっと難しいコードが出てくるんだよね。《Oh yeah, it’s alright》のとこかな。
KEN あぁ、何か所かディミニッシュコードを使ってると思う。
Jun-Gray 最初、ギターと歌メロがぶつかってるんじゃねえのって思って、そこは俺がベースでポップにしてやらないとダメなんじゃないかって思ったりもして。たまにかっこつけてそういうコードを使うから。
KEN いや、違う違う。曲が求めてるんです(笑)。
―― たぶん、そのおしゃれなコードの使い方と関係していると思うんですけど、サビの《It’s gonna be OK》から《These magic words》と歌う直前にミッドロウで鳴るギターフレーズが……。
KEN 巻弦の。
―― はい。あのフレーズ、すごくいいですよね。
Jun-Gray 俺が考えました(笑)。
KEN ハハハ。そうだったかもしれないです(笑)。
―― 「These Magic Words」は、そういう耳に残るギターのフレーズがいっぱい散りばめられているところも聴きどころになっていると思います。ギターのハウリングがいろいろなところで鳴っているのもいいですね。
Jun-Gray KENが特に好きなんですよ。Minamiちゃんは正反対って言うか、あんまりハウリングを録ろうとしない。
KEN レコーディング現場の話なんですけど、Minamiちゃんはブースにアンプだけ入れて、エンジニアの隣で弾くんですよ。海外のアーティストはほとんどそうやっているですけど、そうするとフィードバック含め、ノイズが入りづらいからクリアな音で録れるんです。それと聴きやすいっていうのもあるのかな。エンジニアが聴いているスピーカーの音を一緒に聴きながら演奏するから。でも、僕はアンプと一緒にブースに入って、ヘッドホンで聴きながら弾くという昔ながらのやり方なんです。ヘッドホンの性能によってはやりづらいこともあるんですけど、僕は空気も一緒に入れたいんです。あと、偶然に出たノイズも。だから、偶然出たフィードバックはもちろん好きですけど、フィードバックだけ別で重ねることもあるんですよ。
―― 「These Magic Words」は冒頭の弾き語りのところから、ハウリングが鳴ってバンドインするじゃないですか。
KEN ギターのボリュームポッドを開ける時のヒューって音ですよね。そういうのがすごく好きで、生々しいと言うか、ライブ感があると言うか。
―― 聴きながら、あれが鳴ると、すごくわくわくするんですよ。
KEN 僕の持論なんですけど、デジタルになって作品がつまらなくなったなっていうのは、世の中の作品もそうだし、自分の作品もそうだし、やっぱりあるんですよね。僕らも今、デジタルで録ってますけど、僕なんかは極めてアナログ的な録り方をしていて。そこに偶然のものとかが入り込むと、人って「なんでこの人、こういうことができるんだろう⁉」っていうふうに感じると思うんですよ。昔は、50年代から始まって、60年代、70年代はピッチなんて直せなかったじゃないですか。
―― はい。
KEN それにもかかわらず、コーラスにしてもみんなしっかりと録っている。そういうものを聴いて、自分もやりたいと思う人もいるかもしれないけど、多くの人は、この人達はすごく努力を重ねてきたのか、元々、才能があったのかわからないけど、誰もができることでもないんだろうから、この曲は特別なものなんだっていうことをキャッチすると思うんですよね。それが今の作品には、まったくない。おもしろいと思える作品に出会わないわけですよ。別に、業界批判をするつもりは毛頭なくて、僕の心の中の事実として言っているだけなんですけど、たとえ生で録ったとしても、これだけデジタルなものが並んでいると、一発録りしましたって言っても、いや、どこか直しているでしょって思いますよね。
―― あぁ、確かに。
KEN こちらも長年かけて、そういう耳になってしまっている。それじゃ、おもしろいバンドには出会えない。生のすごさって、そういうところに魅力があったんだなって思います。
interview by 山口智男
Vol.2へ続く...
Interview Vol.02
-- 「These Magic Words」で僕がかっこいいと思ったギタープレイをお伝えしてもいいでしょうか?(笑)
KEN: はい(笑)。
-- これはKEN BANDの得意技かもしれないですけど、2番でミュートカッティングしているところにオクターブ奏法で加えるフレーズとか。
KEN: あれは涙がちょちょぎれますよね。
-- ラスサビ前の間奏から、《Ah Ah Ah》というシンガロングパートに入る直前のギュイーンとか。
KEN: ああ、スライドしてるやつ。6弦でロウフレットからハイフレットにぶーんって。そういうことやる人、今、いないんですよ(笑)。でも、僕はすごく好きで、レコーディングする時は必ずどこかに入れますね。
-- あと、サビが終わった後の音階を下がるコードリフが1回しか出てこないところとか。
KEN: 2回しかやらないで、1回だけっていう。
-- もう1回聴きたいのに、やらないところが心憎いなと、あそこを聴くたび思います(笑)。ギターソロももちろん入っていますけど、大袈裟なソロやリフではなく、そういうウィットに富んだフレーズで聴かせるところが、「These Magic Words」をより聴き応えあるものにしていると思います。
KEN: ありがとうございます。うれしいな。そんなにたくさん聴いてもらえて。でも、そういうところを、僕は聴いてもらいたくて、アンプと一緒にブースに籠って、ギターを弾いているんです。今のエンジニアは本当に相性が合うから、そんなことはないんですけど、普通のエンジニアだったら、さっき言ったブーンみたいなやつは、「今のはなしにしません?」って言うと思います。
-- え、そうなんですか?
KEN: 意外とカットされると思います。
-- でも、ギターソロの直前ってグリッサンドからのチョーキングって多いと思うんですけど。
KEN: ギターソロのフレーズの中だったらわかるけど、曲中のバッキングでやられると、ちょっとぐしゃっとするみたいな感じで言われると思います。
-- あぁ、そうなのか。さっき言い忘れましたけど、ギターソロのビブラートの感じも気持ちいいですね。
KEN: そうですねぇ。……って、自分で目を細めて言っちゃった(笑)。繰り返しになっちゃいますけど、結局はデジタルなんですけど、どこまでアナログ感と言うか、生々しさを残せるかなっていう。ブーンっていうのも聴感上、聴こえない人もいると思うんですよ。楽器に詳しくない人とか、そんなにロックを聴いてない人とかは。ただ、感じるとは思うんですよね。「なんだ、この感じは!?」って。そういうふうになってくれたらいいなと思って、いつもやってます。
-- サウンド面ではそんな聴きどころがある「These Magic Words」ですが、歌詞もまた聴きどころで、「Time Waits For No One」同様に子供の世代に対するメッセージになっていますが、こういうことを考えるきっかけがあったんですか?
KEN: きっかけは特に憶えてないですけど、「Time Waits For No One 」と「These Magic Words」、それと先に話しちゃいますけど、「Bitter Truth」の3曲は、子供世代に向けた曲なんですよね。
-- はい。
KEN: 表現はそれぞれに違うけれども、視点は親的なんです。あ、「These Magic Words」は、なんでそういう歌詞になったのか思い出した。僕、今、小さい子供がいるんですよ。もうすぐ3歳なんですね。たぶん、「These Magic Words」の歌詞を書いていたのは一昨年の暮れだから、子育ての真っ最中だったんですよ。そうすると、親として、新しくこの世の中に生まれてきた、すごく未熟で、守られるべき命を、どう守るかおのずと考えるんですね。専門的な話ですけど、親って第一社会と言われていて、子供が接する一番最初の社会なんです。そこから受ける影響ってものすごく大きいわけですよね。三つ子の魂百までっていう諺と近くて、要するに子供が小さい時に親はどれだけ安心感を与えてあげられるかってことなんですけど、不安な時、抱きしめてくれるんだ、親はってことを教えると言うか、刷り込んでいくわけですよね。これはそういう歌です。
-- なるほど。
KEN: ハハハ。Junちゃん、今の聞いて、「こいつ、頭いいと思われたいと思ってる」って絶対、思ったでしょ?
Jun-Gray: いやいやいや、別にいいんじゃない(笑)。
-- Junさんは、横山さんがこういう歌詞を書くようになったことについて、どんなふうに感じていますか?
Jun-Gray: 「Bitter Truth」みたいに、すごく厳しい現実もあるんだよって言ってる曲もあるけど、「These Magic Words」のサビで言っているように《大丈夫さ。そのうちオッケーになる》みたいなことは子供に対してももちろんなんだけど、聴いた人は自分に対して言っているんだって感じると思うんですね。俺はよく楽天家って言われるんですけど、小さい時から、「These Magic Words」じゃないけど、どんなトラブルになっても、「まぁ、いいや。とりあえず何とかなるでしょ」とか「時間が解決する」とかって思う人だったんです。確かに小さい子供もいっぱい困難はあるのかもしれないけど、「まぁ、でも何とかなるんじゃない?」っていう救ってあげられる言葉がないと、結局、自ら死を選んでしまうって言ったら極端かもしれないけど、逃げ場がなくなってしまうから、結局、何とかなるもんよ、人生はそういうものじゃないかなって自分が思っているところもあるんでね。
KEN: 事実、大丈夫じゃなかったとしても大丈夫って言ってくれる人がそばにいるかどうか。
Jun-Gray: そうそう。
KEN: そういうことを子育てしていると、思うんですよね。言ってあげたいし、僕も言ってほしかったしって。だから、すごくイマドキの言葉で言うと、主語がでかい歌と言うか(笑)。最近使いますよね。主語がでかいって言い方。でも、主語がでかいとは違うのかな。要するに、意外とでっかい歌ですね。しかも、そうやって子供に言っていると、自分にも跳ね返ってくるんですよ。ほんとに。何かあっても、まぁ大丈夫。それが実際、そうならなかったとしても、そうやって自分に言い聞かせることは希望にはなる。だから、赤ちゃんに教えているようで、赤ちゃんから教わっているんですよね。育児は育自ってよく言うじゃないですか(笑)。ふざけんなよって思うんですけど、結局、そうなのかなってやっぱり思いますね。わかる? 育児は育自って、Junちゃん。
Jun-Gray: 何それ?
KEN: 育児は自分も育てる育自でもあるっていう。
Jun-Gray: あぁー、自分の自ね。
KEN: 一時期よく言われていて、何うまいこと言ってんだって思ってたんだけど、あぁ、そうなのかもって。ハハハ。
-- それで、《But something you’ve taught me as well(でもオレがお前から教わったことでもあるんだ)》という歌詞があるんですね。
KEN: はい。うちの奥さんと子供の関係を見ながら、そう思ったんですよ。責任ではなく、本能でやっていると思うんですけど、すごいなと思いました。あと、家族の話と言えば、言っておかなければいけないことがあるんですが、いいですか?僕、離婚しているんですよ。それで「健って家族愛を売りにしているくせに」ってずいぶん言われたんです。でも、僕は家族のことを語ったり、歌にするのに、家族愛を切り売りしているつもりなんかなかったんです。自分にとって当たり前のこと過ぎて、売りになんかした覚えはないんです。
そう思われて、その点で支持してくれていたとしたら、もうそれは「ごめんよ」としか言いようがないんですが。それで今回「These Magic Words」の歌詞の原風景として、いまの再婚した家庭から得たものが影響してて、今日も言葉にもしましたけど、やっぱり家族愛を売りはしていないよ、とはっきり言っておかなければいけないと思いました。子供への愛情は離れたって1ミリも変わらないほど確かなものだけど、夫婦は男と女ですからね。まるっとした家族愛なんか持っちゃいませんよ。ごめんなさい、話が逸れました、どうぞ。
-- 僕は子供がいないんですけど、Junさんはいらっしゃるんですか?
Jun-Gray: 2人います。専門学校生と高校生。
-- じゃあ、「These Magic Words」の歌詞は、親としてもかなり共感できるわけですね。
Jun-Gray: そうですね。出来が悪い2人なんですけど、「These Magic Words」ができる前から、「まぁ、何とかなるんじゃない?」「自分が楽しいと思うように生きなさい」と言ってましたけどね(笑)。
-- Junさんが楽天家になったのは、いつ頃からだったんですか?
Jun-Gray: 楽天家だとは自分では気づいてなかったんですよ。周りから言われて、ああ、そうなのかって。「何も考えてないでしょ」って言われることもありますからね(笑)。
-- 気づいたら、何とかなる。大丈夫だというふうに思うようになっていたんですか?
Jun-Gray: 仕事の面で言うと、30過ぎくらいの時が一番ダメージを食らてっていて、「うわ、しんどい。ストレスマックス」みたいなことがあったんです。血尿まで出てみたいな。でも、そういう時も、あー、でも半年後には何とかなってるんじゃないかなって思っていたと言うか、思うようにしていたと言うか。こんなしんどいことはずっと続かねえだろって。そうすると、意外とそういうふうになっていくものなんですよ。でも、そのうち何とかなるでしょっていうのも自分に対する言い聞かせでもあるから、思ってないと、どんどん悪い方向に行くかもしれないから、思うことが大事だと思ったりもします。
KEN: そう。結局、何とかなるでしょって、何とかするのは自分なんですよね。時間とか、環境とか、外的要因が補正してくれることもあるけど、結局、そういうふうに思い込んで進んでいくのは自分自身なので。Junちゃんが40半ばの時に。
Jun-Gray: 44だったね。KEN BANDに入ったのは。
KEN: そこからこの人の人柄を知っていったわけですけど、Junちゃんの人柄はバンドにとっては、安心感に繋がっているとすごく思いますね。「しょうがねえだろ」ってよく言うんですけど、でも、結局それだよなって。いろいろ気分的に納得が行かねえなってことがあったとしても、「しょうがねえだろう」って。「しょうがねえだろ」で済ませるつもりではなくて、それが極論と言うか。それを飲み込んで、先にどう進むかっていうのが重要なんだっていう。
-- 魔法の言葉や、願い事は叶うと信じたいという希望を歌う一方で、今回の2曲目の「Bitter Truth」は曲調からというところもあるのかもしれないですけど、歌詞の内容はかなりタフで。
KEN: 「These Magic Words」とは180度違いますね。僕の長男が高校3年生で、卒業後の進路を考えることも含め世の中に出ていこうとする世代なんですよ。Junちゃんちの子供もそうで、そういう世代に向けた歌ですね。今のご時世、ジェンダー論とか通用しないかもしれないですけど、この曲にはやっぱり男の子だったらっていうところもすごくあって。
-- わかる気がします。男だったらとか、女なんだからとかって、確かに今の時代、もう古いのかもしれないですけど、男らしさ、女らしさともに変わらないものもあるんじゃないかと思うところもあります。
KEN: 変わらないですよね。確かに男と女だけじゃないっていうのは、僕もちゃんと理解しているんです。周りにそういう人達もいるから。なんだけども、そういうところとはまた別で、自分が持っている風景には、男だったらよぉっていうのは常にありますね。
-- それを他人に押し付ける気持ちはこれっぽっちもないけどという話ですよね。ところで、こういう2ビートのメロディックハードコア・ナンバーは作ろうと思って作るんですか? メロディが降りてくる曲とはちょっと違うのかなと思うんですけど。
KEN: 実は、この曲は夢の中で丸々できたんですよ。だから、仮タイトルは「夢」だったよね?
Jun-Gray: そうだったね。
-- 夢の中で曲ができることは、よくあるんですか?
KEN: たぶん初めてなんじゃないかな。それを形にしてみようと思うこともたぶん初めてで。何かで誰かがこの曲を演奏しているんですよ。
-- あ、夢の中で。
KEN: 特にサビのダ・ダッダダ・ダッってブレイクがしっかりと夢に出てきて。
-- これもバンドに持っていった時は弾き語りだったんですか?
KEN: そうです。「昨日、夢の中でこういう曲ができてさ」って(笑)。でも、夢に出てきたものをそのままやるわけには行かないから、コードの補正なんかはもちろんしましたけど。
-- 「Bitter Truth」の演奏面での聴きどころは?
KEN: EKKUNのドラムなんじゃないかな。けっこう竜巻まくってるんで。
Jun-Gray: 奴の得意な感じだと思う。
KEN: この曲、もしかしたら2月にレコーディングした曲の中では一番最初にできたんじゃなかったかな。
Jun-Gray: そうかもね。アレンジ面でもさほど悩むこともなく、全員が得意なことをしながら進んでいったんじゃなかったっけ。
-- Junさんのベースは……。
KEN: 僕が書いた通りに(笑)。
Jun-Gray: はいはい、そうですね(笑)。
-- 無骨にリズムを刻みながら、サビに加えたフレーズが動くパッセージが耳に残りますね。
Jun-Gray: 「Sorry Darling」のような曲に比べると、やっぱり曲調が得意と言うか、KEN BANDでよくやっているやつなんで、そんなに考えなくてもすらすらと出てきちゃうんですよ。才能あるから。
KEN: ハハハ。
Jun-Gray: ハハハ。サビが3回あって、3回とも違うフレーズを入れてるんですけど、そういうのが好きなんです。それに3回とも同じだったら能がないじゃないですか。だから、3つとも違うフレーズを入れてやれって。
-- この曲、左側ですっとフィードバックが鳴っていますね。
KEN: 1番のAメロですね。フィードバックと言うか、単音を重ねた和音をずっと鳴らしているんです。
-- それは後から重ねたんですか?
KEN: そうです。
-- どういう効果を狙って?
KEN: 緊張感を出したいと思ったんです。サスペンスの効果音でよくあるじゃないですか。そういうものに近いですよね。
Jun-Gray: そういうちょっとしたことでもけっこうこだわって録ってるよね。1回しか録ってないわけじゃなくて、何回か録って、これよりもこっちのほうがいいって選んでるんですよ。
KEN: 和音もいろいろ試しましたね。むしろ決まったコードやメロディよりも、レコーディングはそういうところが楽しくて、楽器に詳しくない人、ロックをあまり聴かない人の耳にどう入っていくかなっていうのを考えてやるんですね。そういう音効って言うのかな。ドラマやCMで、あ、この音ってこう出しているんだっていうのあるじゃないですか。そういった要素もレコーディングに加えるのが僕はすごく好きなんですよね。
-- そういうところに作り手としての思い入れや矜持がある、と。
KEN: はい。あのピーっていう音があるのとないのとでは、もう全然違う曲に聴こえると思うんですよね。
-- 「Time Waits For No One」に《Bitter truth》という歌詞が出てきます。これは偶然なんですか?
KEN: いえ、「Time Waits For No One」ができたとき、「Bitter Truth」がすでにあって、同じテーマだから、《Bitter truth》って言葉を「Time Waits For No One」の歌詞に入れちゃおうって。最初に「Time Waits For No One」を聴いた人は、《Bitter truth》って何のことかわからないけど、今回のシングルで「Bitter Truth」を聴いて、あ、もしかしたらこのことを言っているのかなっていう連想ゲームとしてもおもしろいと思いました。割とスキップされがちなところだと思うんですけど、よく気が付いてくれましたね。作り手はそういうところに気づいてほしくて作っているから、すごくうれしいですね。リスナーにもそれぞれにそういうストーリーがあったりするのかなって思うと、たとえそれが僕らは全然狙ってないことだとしてもワクワクしますね。それこそグレートフル・デッドのファンは、「この曲の次にこの曲をやったってことは、俺達にどんなメッセージを伝えようとしているんだろう?」って考えたわけじゃないですか。本人達はそんなことは全然考えてないのに、みんなキマッちゃってるから(笑)。
Jun-Gray: 妄想だよ(笑)。
KEN: 僕もそういうのすごく好きでいろいろなアーティストの歌詞を読んでこれって何のことなのかなとか、昔のことと関係あるのかなとか、そういうことを探したりしますね。
interview by 山口智男
Vol.3へ続く...
Interview Vol.03
―― さて、3曲目の「Sorry Darling」はマージービートともフォークロックとも言えるポップナンバーです。「Better Left Unsaid」にもマージービートっぽい魅力を感じましたが、「Sorry Darling」はどんなイメージの下、作っていったんですか?
KEN: 僕が持っていった時はまさしくフォークロック的なものを狙っていたんですけど、なぜかメンバー4人の解釈が違って、いいところになかなか着地しなかったんです。けっこういろいろやったよね? 僕がアコギを持っていって、いろいろ試したんですよ。
―― アコギですか!?
KEN: アコギを持って歌う曲にしてみようってやってみたりもしました。
Jun-Gray: リズムで言うと、EKKUNはこんなにテンポの遅い8ビートは叩いたことがないってところで、ちょっと苦労したかもしれない。俺はブリティッシュな感じはしてたんですけど、Minamiちゃんがアメリカンな解釈をしていて、そういうところで、最初はなかなかうまく進められなくて、意外とアレンジに時間が掛かりましたね。
KEN: メロディとコード進行ははっきりしていたんですね、もう。メインリフも。それをどう調理するかって、案外、僕らには珍しい悩み方をしましたね。
―― 紆余曲折を経て現在の形に着地した、と。
KEN: 結局、レコーディングの場で決まりました。
―― アコギを持って歌う曲というイメージのまま進んでいったら、そういう曲になっていたかもしれない?
KEN: そうですね。ただ、それだけでは終わらせたくなかったんですよ。レコーディングではアコギも入れましたけど、もうちょっとロックに寄せられないものかって、音色も相当考えて、使うギターも試行錯誤して。珍しいギターを使って、僕は録りました。いや、珍しくはないんだけど。
―― 横山さんが普段、あまり使わないギターを使ったわけですね。
KEN: クセのあるギターが好きなんですね、僕は。なんだけど、この曲は最終的にそんなにクセのないYAMAHAのレブスターってエレキギターでレコーディングしました。割とカチッとした音が出るんですよ。そしたらハマりが良くて、それでもMinamiちゃんは、「え、これかな」って言ってた気がするな。
Jun-Gray: やっと着地したくらいの感じの曲だったんだと思います。「いいんじゃない? これで。OKでしょ。形になったでしょ」って思ってたけど、Minamiちゃんは「あれ?」って思うところがあったのかもしれない。
KEN: たぶん、Minamiちゃんはもっと壮大にしたかったんだろうね。
Jun-Gray: そうかもしれない。
KEN: オブリを弾いているのはMinamiちゃんなんですよ。そのフレーズを聴くと、たぶんもうちょっと壮大な、それこそアメリカの大地みたいなさ。
Jun-Gray: そうね。ブライアン・アダムスみたいなのをイメージしてたと思うんだけど、俺はラーズみたいなブリット・ポップとか古いパンクっぽいものをイメージしていて。ベースのフレーズはクラッシュの「Charlie Don't Surf」という曲に勝手にオマージュって言うか、このフレーズ乗っけられるじゃんって持ってきたりもして。
―― その曲はどのアルバムに入っているんですか?
Jun-Gray: 『Sandinista!』ですね。
―― うちに帰って聴いてみます。Junさんはギターソロの裏でベースソロと言ってもいいフレーズを弾いていますね。
Jun-Gray: そうですか? そんなに弾いてないですよ(笑)。フレーズでちょっと遊びましたけど。
KEN: 因みにギターソロもMinamiちゃんです。
―― さっきマージービートっぽいと言いましたけど、横山さんの歌い方のせいか、歌メロがデコボコしていて、単にマージービートっぽいとは言いきれない、KEN BANDならではのものになっていますね。
KEN: エモーショナルに歌いたくなってしまいましたね。
―― それは歌詞によるところが大きいんですか?
KEN: いや、曲調かな。歌詞は自分で書いておいて、何のことかわからないんですよ。
―― えっ、そうなんですか?
KEN: 何のことについて書いたのかいまいちわからない。
―― いや、ソングライターが曲を書く時の舞台裏や、ライブを終えて、家に帰った時のロックスターの孤独を歌っているんじゃないかと思いましたけど。
KEN: そうですね。なんとなく世俗と離れた人の視点みたいなことは書きたかったんですけど、結局、何のことかいまいちわからない(笑)。それで、なんで《Sorry Darling》なのかもわからないんですよ。これね、歌詞を書いたのが明け方だったんで(笑)。
―― 確かに《Suddenly came to my mind, to go see the sun outside(ふと思い立って 外に太陽を見に出たんだ)》と歌っていますけど、お客さんに対して、《Sorry Darling》って歌っているんじゃないかって。
KEN: なるほど。そうやって説明していこうかな(笑)。
―― 《I think I know what’s wrong(なにが問題なのか オレにはわかってる)》と歌っていますが、本当にわかっているんですか、それともそれもわかっていないんですか?
KEN: うーん、わかってるけど、言えないですね(笑)。社会にはいろいろな問題があって、人それぞれに、それに対する見方も取り組み方も違うわけですけど、政治家、何やってるんだってところもあるじゃないですか?
―― はい、たくさんあります。
KEN: そういうことに対して、僕なりに問題の解決方法はわかってるけど、自分に手の付けられることではないと言うか、まぁ、そんなようなことだと思います。
―― いただいた資料には、「横山が書く詞はこれまで以上に彼の生身が感じられる内容になっている」と書かれていて、僕もそういうふうに思うんですけど、ご自身でも生身の横山健が以前よりも出てきたという自覚はありますか?
KEN: ありますね。特に歌詞は去年の暮れから今年の頭に掛けて書いたんですけど、その時期、精神的に内に向かう時期だったんですね、たまたまかもしれないけど。だから、今回のシングルの曲達は、今までもよりも一歩進んで、個人的な精神世界みたいな感じはあると思います。書いている時は個人的すぎて、要するに自分にとっては当たり前すぎて、こんなことを曲にしてもなと思ったんですけど、今、見ると、なかなか興味深いと言うか、いいですね。
―― Junさんはそんな歌詞の変化について、どんなふうに感じていますか?
Jun-Gray: コロナ禍も含め、今の時代も関係していると思うんですけどね。俺が入ったのが14、5年前なんですけど、最初に参加したのが『Four』ってアルバムで、その頃は、今と比べると、ぶっちゃけどうでもいいようなお遊びの歌詞って言ったら、言いすぎだけど(笑)。でも、そういうことまで題材にしていると言うか、俺が入る前の曲もそうなんですけど、『Four』の時はそういう余裕って言うのかな。まだ平和だったと言ってもいいと思うんだけど、その後、東日本震災があって、『Best Wishes』を作ったくらいからシリアスな曲も増えてきたような気はします。今振り返ると。で、ここ最近になって、コロナ禍が来ちゃって、戦争まで起きてちゃんと伝えたいことがあるって感じになっているんじゃないかな。だから、これで日本って言うか、世の中がよくなってくれれば、どうでもいいようなこともまた歌うのかもしれないけど、そういうモードではないんだろうな。
KEN: さっきJunちゃんが言ってた『Four』って2010年のアルバムで、僕は40歳になる手前だったんですね。当時は震災もなければ、コロナ禍もなかった。まぁ、世の中はそれなりに悪かったけど、今とは質が違っていた。音楽もちゃんと聴かれていた。まだそういう時代だったんです。だから、個人的な思いで言うと、この十何年の変化は相当でかいですね。
―― そういう時代に攻撃的に外に向かっていくのではなく、横山さんは内側の精神世界に潜っている、と?
KEN: そうですね。それこそ『Four』の時に怒りを表に出したつもりだったんですよ。まだ当時は怒り甲斐や叫び甲斐があったかもしれないですけど、うーん、今はそれがたぶん徒労に終わるんだろうな。徒労って言うと、かっこよすぎるかな。簡単な言葉で言うと、世の中に怒るだけエネルギーの無駄と言うか、相当冷めましたね。世の中に対しては。
―― そうですね。結局、日本って何も変わらないんだなって思いながら、それに対して怒ることに対して、おっしゃるとおりエネルギーの無駄使いと思うことが多々あります。話題を変えて、今回、初回盤に付くDVDについても聞かせてください。DVDには5月の日比谷野外大音楽堂公演からの5曲が収録されています。
KEN: 辛うじて出来が良かった5曲を入れました。
―― え、そうなんですか。選曲理由はそれだけじゃないと思うんですけど(笑)。
KEN: もちろん、他にもあったんですけど、このバランスがいいかなってなりました。
―― 野音で見ている時はわからなかったんですけど、JunさんはLAUGHIN' NOSEのTシャツを着ていたんですね。
Jun-Gray: そうですね。戦争反対の。野音をやる1か月くらい前にたまたまLAUGHIN'が俺の住んでる八王子にライブで来たから遊びにいったんですよ。その時に買ったTシャツです。あと、LAUGHIN'の野音っていう思いももちろんあって。
―― あぁ。
Jun-Gray: 野音って言ったらLAUGHIN'だよねっていうのが俺は古い人間だからありましたね。
―― 40年くらい前の話ですけど、LAUGHIN' NOSEって、それまでゴリゴリのハードコアをやっていたのに「I CAN'T TRUST A WOMAN」から急にポップになったじゃないですか。あの時、衝撃じゃなかったですか?
Jun-Gray: 衝撃的ではあったんですけど、「I CAN'T TRUST A WOMAN」の前に「GET THE GLORY」があったから。あの曲がすごくポップだったじゃないですか。でも、あの当時、俺もどっぷりあのシーンにいたんですけど、UKのハードコアからもアブレシブ・ホイールズをはじめ、ちょっとポップなバンドが出てきてたんで、そんなに違和感はなかったと言うか、日本のパンクバンドの中にもこういうふうにポップになっていくバンドもいるのねって思ってましたね。LAUGHIN'はそこからどんどんポップになっていくんですけど、「GET THE GLORY」とか「聖者の行進」とかやってた時は、そんなに意外でもなかったです。
KEN: アブレシブ・ホイールズって「聖者の行進」やってなかったっけ?
Jun-Gray: やってた。言い方は悪いけど、真似たなって思った(笑)。
―― 当時、パンク好きの友人達の間では「急にポップになりやがって」と言ってましたけどね(笑)。
Jun-Gray: 売れ線狙ってんだろって思った人もいたと思うけど、両方だと思いますよ。俺、LAUGHIN’に直接聞いたことはないけど、アブレシブ・ホイールズやアディクツとかの影響も受けつつインディーズシーンでガツンと売れたるでってところもあったと思うんですよね。俺は逆にそれがかっけーとも思っていました。
―― すみません。余談でした。野音公演についてもうちょっと聞かせてください。今回、DVDに収録されている「Let The Beat Carry On」他の何曲かで横山さんはテレキャスターを弾いていましたが、テレキャスターのイメージってそんなになかったので、野音で見たとき、ちょっと意外でした。
KEN: 一昨年ぐらいから弾くようになったんですよ。最初は青いテレキャスターを海外の工房で作ってもらって、それからFENDERさんと縁ができて、FENDERのテレキャスターを弾くようになりました。
―― 野音で弾いていたテレキャスターのティキのイラストは横山さんが描いたそうですね。
KEN: はい。全部、自分で描きました。それをプリントしてもらって、ピックアップにハムバッカーを乗せてもらって、すごくカスタムしてもらったんですね。
Jun-Gray: シェイプはテレキャスターだけど、王道のテレキャススター音じゃないんだよね。
KEN: 横山流テレギブ(笑)。
―― なるほど。テレキャスターとギブソンのいいところどりというわけですね。イラストと言えば、前回のインタビューで聞きそびれてしまったんですけど、今回のシングルシリーズのジャケットは横山さんが描かれているじゃないですか。不勉強で申し訳ないのですが、イラストはいつ頃から描かれているんですか?
KEN: コロナ禍でやることがなくなったとき、家でちょっと描いてみたんですよ。僕、観葉植物が好きなので、観葉植物の絵を、色鉛筆を使って描き始めたんです。最初はヘタクソで酷かったんですけど、描くって行為自体は楽しいもんだなって思いました。その前からと言うか、小さい頃から漫画家になりたかったんです。小学生の低学年の頃ですよ。『ドラえもん』に似たようなパクリみたいな漫画を自分で描いては友達の間に回して、読んでもらってたんです。だから、絵心はゼロではないんです。それもあっておもしろいもんだと思いました。2020年の『Bored? Yeah, Me Too』の時にレーベル直販でやるし、ある程度、経費も節減したいしってことから、自分で描いてみて、自分の作品だったら、まぁいいのかなと思うようになりましたね。
―― シングルシリーズはカラーなんですけど、画材は何を使っているんですか?
KEN: 実は僕、白黒しか描いていなくて、ダイスケホンゴリアンに色を塗ってもらってるんです。自分の中にちゃんとイメージがあって、「この色で塗って」と指定するんですけど、自分で色を付けるにはテクニックがまだ追い付かなくて、『Better Left Unsaid』からの今回の3作は、僕が線だけ描いたものにホンゴリアンに色を付けてもらってます。
―― 線画は何で描いているんですか?
KEN: 鉛筆です。
―― タトゥーアートっぽいタッチの絵ですよね。
KEN: 基本、トラディショナルなタトゥーを参考に描いています。
―― ジャケットのイラストを手元に置いておきたいというファンは少なくないと思うんですけど。
KEN: シングルシリーズとして統一感も出したいし、描くことでお客さんにも歓んでもらえるかなと思って、けっこうがんばりましたね。今回のやつは1回作ったんですけど、全部描き直したんですよ。色を付けたら、ヘタクソに見えちゃって、「ごめん、もう1回描くわ」って。
―― ガイコツがスロットマシーンに寄りかかっている絵柄は、どんなところから?
KEN: タイトル曲の「These Magic Words」は希望を持たせる曲なだけに、ジャケはちょっと皮肉をきかせたいと思って、スロットマシーンで666が出ちゃってるけど、それでも余裕で笑っているガイコツっていうのを描いてみました。
―― 今後も描き続けるんですか?
KEN: チャンスがあれば。自分の作品だったらできそうですね。
―― 描いてほしいって言われませんか?
KEN: 1人だけいたんですよ。先輩なんですけど、「横山、外注は受け付けているか?」って言われて、「いや、ごめんなさい」って丁重にお断りしました。そうですね、自分達のマーチャンとか、シングルとか、何かの折には描きたいと思います。次のアルバムはしっかりホンゴリアンに頼みますけどね。
―― ジャケットも魅力のシングルシリーズ、振り返ってみると、かなり多彩な曲が揃いましたね。
Jun-Gray: でも、『These Magic Words』のインタビューで言うのも変だけど、この後に控えているアルバムも負けてねえよって気持ちもあるんで(笑)。
―― あー、なるほど。そこも聞かせてほしかったところです。シングルシリーズの8曲がこれだけ振り幅があるので、アルバムに対する期待がさらに高まったのですが、シングルシリーズとはまた違う振り幅の曲もあるんですか?
KEN: ありますね。あんまりやったことないけど、インストも入ってるんですよ。めちゃかっこいいですよ。
―― どんな感じのインストなんですか?
KEN: どんな感じなんだろうね。
Jun-Gray: どういう感じ? うーん。
―― たとえばサーフギター・インストみたいに一言では言い表せない感じですか?
KEN: サーフロックに近いと思うんですけど、ディック・デイルみたいではないですね。もうちょっと、何だろう? ベンチャーズに近いのかな。
Jun-Gray: うーん、サーフロックっぽくもあるけど、スカパンクっぽくもあるし。
KEN: スカとサーフとオールディーズが混ざったような。実はそれがタイトルチューンなんです。
Jun-Gray: 初めてやったけど、うちらっぽいと思いますけどね。
KEN: シングルの多彩さは、誤解を恐れずに言うとちょっととっちらかった多彩さだと思うんですよ。アルバムは統一感があって、引き締まった印象があるんですよ。
interview by 山口智男
![Ken Yokoyama New Single [These Magic Words] リリース特設サイト](./assets/img/mv-description.png)
![Ken Yokoyama New Single [These Magic Words] リリース特設サイト](./assets/img/release-description.png)







![Ken Yokoyama [These Magic Words] Official Interview](./assets/img/title-interview.png)