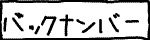『横山健の別に危なくないコラム』
Vol.98
「The Gift tour 2017」、終わってしまった。
オレは物事の終わりに対してかなりドライな気持ちを持っている。何事に対しても、始まりはワクワクするが、終わる時は「終わっちまうもんはしょうがない」、「そんなもんだ」と自然と思えてしまう、そういったドライな人間だと自分自身を思っている。
でも今回のツアーは、そんなオレでさえ「終わっちゃったなぁ……」と寂しさを覚える。始まりも終わりも、何ヶ月も前から決まっていたにも関わらず、それでも寂しさを覚える。それほど楽しく、充実した日々であり、良いツアーだった。
このまま楽しかったツアーの事だけつらつらと書いても良いのだが……寄り道したりしながら、ずいぶん前のことから話すことにしよう。

「パンパンに膨れ上がったさいたまスーパーアリーナでロックする、
世界最強のロックンロールバンド photo by teppei kishida」
「ハイスタの Air Jam 2011 以降の変化」
今年は1年間、年明け早々に本格的に始まった曲作りから、夏のレコーディングを経てツアーに至るまで、ハイスタとして存分に駆け抜けた。
その分2017年の Ken Band は活動が少なかった。「今年は Ken Band の動きが少ない!」とクレームも頂戴したりしたが、「ハイスタで新曲作ってるからあまりライブも入れてないんだよね」などと公言できるわけない。黙っているのも辛かったが、まぁそれに触れるわけにはいかない。
ナンちゃんは案外 Namba69 との両立を上手くできる様だし(メンバーからの突き上げもかなりあるようだがw)、ツネちゃんも NHK の音楽番組にレギュラー出演するなど定期的に活動していた。しかしオレは、いまだにハイスタと Ken Band の両方に効率良く時間や気持ちを割くことができない。少しならできる。しかし効率良くはできない。
今更ながらではあるが、どうやらオレはそういう作りになっている様だ。
「今年はハイスタの年にする」というのは、去年末の段階でなんとなく決めていた。「アルバムを作って、大きなツアーをする」ということ。それには持てる気持ちや力の全てをそっちに注がないと、オレにはできないことを意味した。やろうと思えばできるが、そんな程度のことならやりたくない。その程度にやることでは、その程度の作品しか作れないし、その程度のライブにしかならない。それはやりたくない。やりたくないなら、やる意味がない。
Ken Band のメンバー、Pizza Of Death のスタッフに、「2017年は新しいハイスタンダードに向かう」旨をしっかりと話した。
話は遡るが、ハイスタは2011年の東日本大震災を受け再始動した経緯がある。この時は自分のためではなく、日本のためだった。本気でそう思ってた。そういうとなんだか押し付けがましく聞こえてしまうが……。それが自分のためだった。つまりは「人のためが自分のため」だったのだ。
それ以降、オレの気持ちは少しずつ変わっていった。
たとえば2012年に Air Jam を開催した勢いで、2013年にも開催することもできた。そんな話も持ち上がった。でもオレは新曲もないまま「人のためにやるハイスタ」としてズルズル行きそうなのがイヤだったので、話し合って開催を取りやめてもらうことにした。
定期的に開催することの大事さも理解する他方、現在進行形のバンド Ken Band をやっている身として、「望まれるているんだからやるか。新曲はないけど、昔の曲でみんな喜んでくれるでしょう」という気持ちにはこれっぽちもなれなかった。
「ハイスタをやるなら、自分から望んで自分のためにやりたい」と、オレは思い始めていた。
Air Jam がなければハイスタは止まってしまう状況だった。新曲を作れば済む話だと思うだろう。しかしそれも、その当時のオレ達には難しいことだった。別にオレが拒否していたわけではない。説明できないが、新曲作りになど、とてもではないが取りかかれる状態ではなかった。
その結果、2年間沈黙した。沈黙したくてしたのではない。結果的にそれだけの時間がかかってしまったのだ。一から考え直す必要があった。ハイスタンダードをやる意味を考え直す。いまだに人気があるっぽいからやる、じゃ情けない。自分達で心の底から「やりたい」と望む必要があったのだ。「やりたいと望むならどういう在り方を目指すか」、共通認識を持つ必要があったのだ。簡単な話なようでいて、実に難しいことだ。
たまにスタジオに集まっちゃ、新曲作りに着手するわけでもなく、前の曲を練習するでもなく、話し合いをした。たわいもない話から核心に迫る話まで、とにかく話をしてた。
しかしこの時間がやっぱり大事だったのだと思う。きっと3人それぞれ考えたと思う。2000年に活動停止した後に新しくそれぞれが始めたことや、変わっていった生活環境との釣り合い。お互いの関係性を見つめ直すこと。ハイスタというバンドの新しい在り方。それぞれが考えたと思う。
動くチャンスが巡ってきたのは2015年の秋。アメリカでの所属レーベル Fat Wreck Chords が25周年を迎え、世界各国で25周年記年ライブを開催していた。それが日本にも来ることになり、オレ達は Fat のバンドとして出演オファーを受けた。これが3人にとって「やりたいからやる」と考えられるようになった大きな転機だったのではないか。
同じ時期にいくつかイベント出演のオファーも受け、2015年末に3本のイベントに参加した。そしてイベントに向けて練習スタジオに入りながらも、探り探りではあったが新曲を作り始めることができた。その「新曲を作っている」という事実がステージに上がる大義を与えてくれたと考えている。
そしてそれは2016年のシングル「Another Starting Line」として結実した。
オレ達は数年かけて「震災を受けて再び集まったバンド」から「やりたいからやるバンド」へと変化を遂げつつあった。
2016年末に福岡で開催した Air Jam 2016 は「やりたいから」という理由だけでやることができたように思う。他に理由は必要なかった。
そのステージで、新曲として「Another Starting Line」をプレイした。新曲を携えて Air Jam のステージに上がれたことは大きな喜びと刺激になり、自分達は現在進行形のバンドなんだと思わせてくれた。
そしてその気持ちは今度は、アルバム「The Gift」へと繋がっていった。
後は一つ前のコラムで書いた通りだ。
5年間の間にこれだけ心の動きがあったのだ。飽くまでもこうして書いていることはオレの心の動きで、ナンちゃんにはナンちゃんの、ツネちゃんにはツネちゃんの心の動きがあったのだから、それは時間はかかる。
ハイスタは3人が納得しないと、決して動かない。しかし5年かけて、みんなで考え抜いて、ディスカッションして、行動して、やっと「自分達が楽しむためのハイスタ」を手に入れられたのではないかと思う。
これは90年代のハイスタとは全く違う、新しい感覚だ。
バンドなんかみんな成り行きで組む。「ベースがいないから、誰々の知り合いに誰々といういまバンドやってないヤツがいるらしい」とか「あの人のバンドが解散したらしいから声かけてみるか」とか。どのバンドも最初は長続きさせることなど考えてない。そこまで考える余裕はない。だって新しく組む人の深いパーソナリティーなど、その時にはわからないのだから。当然、というか結果的に成り行きなのだ。
それが、メンバーの一人に突出した才能があってそれにもたれかかったり、全員が気持ちを心底通わせあったり、奇跡的な化学反応がメンバー間に発生したり……そんなような偶然が起きた時にバンドは成功し、長続きしたりする。
とにかく基本は成り行きだ。
ハイスタもそうだった。1991年に成り行きで結成された。オレ達には化学反応が起きた。スタジオで演奏すると、このメンツは特別だ、そう思えた。しかし長く続けることなど考えていなかった。成功すること……時代が時代だったので「カッコ良く成功すること」には拘った。そこだけは共通認識を持っていた、はずだった。しかし成功するにつれ、3人それぞれの「カッコ良く」がずれていった。
バンドはどんどんデカくなっていったが、それはもはや化学反応にのみ頼った成功だった。お互いの大事さもわからなかったし、敬意も持てなかった。そして2000年の千葉マリンスタジアムを最後に活動不全に陥った。
当然のことながら、ライブなどで公に出ない間も、人々はオレ達3人個々を「ハイスタンダードの○○」と認識する。活動してないとしても、一生ハイスタンダードと言われる。オレは Ken Band を始めた時に、それを身を以って体験し、「10年やって、やっとハイスタとは別なんだと認識され、初めてスタートラインに立てるんだ」と腹を括った。
成り行きで始まったものがこんなことにもなってしまうのだ。それほど「元々どこから出てきた人なのか」というのはリスナーやファンにとって大事なことなのだ。
一度止まってしまったバンドが、若かりし頃放っていた輝きを上回ることはほぼない。
しかし今のハイスタンダードは、絶対に90年代の輝きを上回っている。いや、認めない人もいるだろうから気遣って表現を変えよう。
90年代と全く異質の、当時以上の輝きを放っている。これは自信を持っている。
理由があるのだ。
なぜか。
個人的/主観的な見解だが理由があるのだ。
先述のことと結びつくのだが、自分達の意思で「『成り行き』を『必然』に変えた」からだ。
ものすごいエネルギーを以ってして、オレ達はそれを成し遂げた。
せっかく作り上げたものをぶち壊し、台無しにし、嫌い合い、辛い時期を送り、周りからは有る事無い事言われ、茶々を入れられ、苦い経験をした。しかしまた集まる機会を得た。恐らく皆さんが理解しているハイスタはここまでのはずだ。
しかしオレ達は漫然とやるのではなく、知恵を絞り、新しい在り方を模索した。ここで「『成り行き』を『必然』に変えた」のだ。これに5年を要したわけだ。
最近「ハイスタは仲が良い」と言われるが、3人ともお互いの能力や個性を認めて必要とし、存在に感謝し、ハイスタンダードという集合場所を大事にしようという気持ちを持っているので、それは当然そうなる。90年代後半なんかちっとも仲良くなかった。今の方がいい。

「『成り行き』を『必然』に変えることに成功したハイスタンダード photo by
teppei kishida」
「現在のハイスタを構成する個性」
ツネちゃんは天使だ。自分の独特な世界観を持っていて……ドラマーという弦楽器とは違う役割だというのもあるが、「ツネちゃんワールド」を持っている。ドラムへの探究心が恐ろしく強い。それはドラミングに顕著に表れているのだが、つまりあの人の頭と心の中がハイスタの音楽を特別なものにしている。いや、頭と心の中にあるものだけではなく、直感や感性で叩くセンスもズバ抜けている。時々とんでもなく的外れなこともするが、彼なりのトライで、その姿勢は素晴らしい。考えてのことなのか、センスなのか……普通にやればいいことも普通にやらない。それが曲を一層歌わせる。
若い頃は気難しくて他者を寄せ付けない雰囲気があったが、今は精神的苦労を経験したせいか、とても柔和な雰囲気を漂わせている。天然、いや、天使だ。
ナンちゃんは火の玉のような人だ。ものすごい情熱の塊だ。そして恐ろしいほどピュアで真面目だ。真面目というより、不器用なのだ。情熱の上手い使い方をイマイチ自覚していないところがあり、周囲を悩ます。オレも若い頃はずいぶんそれに悩まされたもんだが、今はオレはそういうナンちゃんを理解できるし、ガイドしようと思えばできる時もある。上手い方向に出た時の彼は無敵だ。しかもオレを信頼してくれて、よーく話を聞いてくれるようになった。もちろんオレもナンちゃんの話を良く聞くようになったが。彼には同じような熱量を持ったパートナーが必要なのだ。今のオレにはそれができる。
とにかく「やるんだ」という情熱がすごい。ハイスタの推進力の源は間違いなくナンちゃんだ。
オレはツネちゃんやナンちゃんよりもズル賢い。計算が効く。今はハイスタのまとめ役でもあると思う。ナンちゃんがまとめる場面も多いが、特に今回のツアーにおいてはオレがまとめ役であり、バンドを牽引していく立場を引き受けた。ナンちゃんがハイスタのエンジンだとするならば、オレは運転手というところだ。二人よりも良く言うと自由、つまりルーズなところも多いが、それは二人ともよく理解してくれていてもう諦めているだろう。でもハイスタの物事をまとめる時はオレの計算が効く。そこも二人ともよく理解してくれていることだろう。
それからオレが一番頑固だとも思う。昔はそのコントロールの仕方をオレもわからなかったが、いまはハイスタをカッコ良く見せるためにその頑固な部分を発揮している。
情熱と真面目さとピュアさ、柔和さとセンスと探究心、計算と自由と頑固、たぶんこれがハイスタの個性なのではないだろうか。
それぞれの個性を誰も潰し合うことはせずに、理解するように努め最大限に引き出す。
3人が力を合わせて、バンドとして同じ方向を向いたら、そりゃ無敵だ。
無敵かどうかは本来は人が判断することだろうが、そういう感覚が自分にあるのだからそうなのだろう。
このお互いの個性を尊重する感じは、おそらく「Another Starting Line」のレコーディングあたりから顕著になってきたように思う。
90年代はレコーディング中、誰が何を録っていてもとりあえずスタジオにいなくては、というある種の強迫観念みたいなものがバンドを覆っていた。なるべく3人同等でなくてはならない、という考えがそういう形で滲み出ていた。お互い口にはしなかったが、ストレスではあったはずだ。しかし「Another Starting Line」のレコーディングの頃からそれぞれのことはそれぞれに任せ、良い意味で分業化が進んだ。それが各個性を際立たせ始めたのではないか。
もちろん「The Gift」の曲作りやレコーディングもこの傾向の中で進み、最終的にツアーで開花することになる。
「ツアーに向けて」
アリーナ9本、ライブハウス4本の計13本、足掛け1ヶ月半に亘るツアー。2016年に「Good Job Ryan! tour」を東北で4本やったが、それからだいぶ時間も経っていたので、全て一からで挑んだ。
まず新曲16曲をしっかり人前で演奏できるように練習し直した。普通アルバムに16曲も入ってると、数曲は「これはライブでやらないよね」という曲が出てくるものだ。でもオレは全曲やりたかった。たとえ結果的に「練習したけどやらなかったね」っていう曲が出てきたとしても、まず全部やれるようになっておかないと話にならない。なにしろツアーも長い上に、18年振りのアルバムを引っ下げてのツアーなのだから。
それに今までの持ち曲を加えて、オレは60曲のソングリストを作った。99年の「Making The Road tour」以来一回もやってない曲、遊びですら演奏してない曲なんかもリストに加えてみた。ツアーの途中で1曲追加したので、最終的に計61曲を演奏した。
元々セットリストに一番強いこだわりがあるのはオレなので、こういったことはオレが担当した。セットリストは宣言通りに毎晩変えた。ちなみに13公演とも、ライブの1曲目は違う曲でスタートした。
ハイスタのセットリストを作ることはオレにとってはものすごく興味深いことだ。ツアーが進むと、始まった当初には気がつかなかったことが見えてくる。「この曲とこの曲を続けると空気感はこうなる」とか「この曲の後のこの曲はテンポ感が悪く感じる」とか当たり前に気がつくだけではなく、メンバーのコンディションを注視するようになる。ライブが続くと、当然ナンちゃんの喉はダメージを受ける。そうすると「喉がフレッシュなうちにこの曲はこのあたりに入れておいたほうが良い」とか、疲れがたまるであろうツネちゃんの足を考え「これだけ速い曲が近いとキツいかもな」などなど。
ハイスタのフロントマンはナンちゃんなので、フロントマンとして作りたい流れがある。なのでまず、組んだセットリストをナンちゃんに投げてみる。そしてナンちゃんの「こうしたい」とか「あの曲を入れたい」というリクエストを聞き、ディスカッションしつつ、最終的なものを作ってメンバーのオッケーをもらう。
そういった課題をクリアしつつ、少しずつ初出しの曲を加えたりしながら、全く違うセットリストを作る。毎回ものすごく悩んだが、とてもエキサイティングな作業だった。
そういうことをバンドとして楽しみたかったし、とにかく観に来てくれる方々に楽しんで欲しかった。複数の公演を観に来る方だって絶対にいるはずなのでそういう方にも全く違うものを観せたかったし、1本しか観れない方にはまるでクジでも引いてもらうかのように楽しんで欲しかった。「あの曲聴きたかったけど、今日は演らなかった」とか「でも演らないと思ってたあの曲が聴けたから嬉しい」とか、人それぞれあろう。なんなら「自分が観に行った日にはやらなかったのに、あそこで演ってるじゃないか!」とか、そんなことすら楽しんでもらいたかった。
延べ人数10万人に観てもらえる規模のツアーだったが、応募自体は40万以上もあった。30万人もの方が応募しても観れないわけだ。それに仕事や育児、闘病などの様々な都合などで応募すら諦めた方だって相当数いたはずだ。きっとそういう方々は SNS などでどんなライブだったか、なんの曲をやったか調べるだろう。そういう方々にも「おー、あの曲演ったんだ!」とエキサイトしてもらえるものにしたかった。
セットリストにそれだけこだわる真意は、ただ単に曲の並べ方にあるのではない。
人前に出る者として、思いつく限りのことを徹底的にやることの意思表示であり、バンドが持つ圧倒的なポテンシャルを引き出すことにある。そしてオレ達3人が楽しむことにある。
そしてオレはツアーを迎えるにあたり、腹の底でズーッと思っていることがあった。
ハイスタを観たい方がいっぱいいるであろうことは分かっていた。そういった人達に「本物のハイスタ、観れたね」で帰すわけにはいかないと考えていた。圧倒的なものを観せないと、一度観た人は二度と戻ってこないって思ってた。
普通は成功すれば人気は不動のものになり、活動は安泰になるものだと考えるだろう。しかしオレはその真逆を考える。頂上に近くなればなるほど、足場は脆くなり危険になる。落下しやすくなるもんだと考えている。
しかもハイスタの場合は、活動停止している数年間の間にも人気は上がっていった。登っている自覚もないまま頂上付近にいるようなものだった。気の持ち方一つで簡単に落ちる。もし圧倒的でなかったら、つまりそれは「ハイスタの人気は、休んでいる間に皆さんの中で勝手に膨れ上がった幻想だった」ということになってしまう。それはダサい。
「そうはさせねぇ」とオレはズーッと考えていた。
オレはオレでそう考えていたし、ナンちゃんにもツネちゃんにもきっと腹の底で「こうしてやる」というものを持っていたはずだ。
3人で、バンドとして、必死でツアーへの準備に取り組んだ。

「自分の部屋でやればいいのに、なぜかカメラマンてっぺいの部屋で明け方までセットリストを考える横山健
photo by teppei kishida」
「ツアー」
初日の渋谷 O-EAST でのライブは絶対に新曲で始めたいと思ってた。新しいアルバムの1曲目「All Generations」でツアーは幕を開けた。それがオレ達がこのツアーで表明すべき……いや、感じてもらいたいアティチュードだった。伝わらないとしても、それはそうしたかった。
初めて新旧の曲をごちゃ混ぜにしてやるライブ……26曲演奏したうちの10曲が新曲だった。慌てたところもあったけど、予想以上に楽しいライブができた。とにかく興奮した。
次の名古屋はハイスタ初のアリーナ公演。どうなるか不安もあった。不安になるあまり、オレは名古屋行きの新幹線に乗りそびれた。しょうがないので自分の車で名古屋まで自走した。周りのスタッフもびっくりして心配もした。でもオレは「なめんじゃねぇよ、道(ストリート)で何年生きてると思ってんだ」と伝えた。「道(ストリート)」の誕生の瞬間である。
それは置いておいて……初のアリーナ公演も、違和感なくできた。「ハイスタがアリーナ、一体どんな雰囲気になるんだろう?」と若干の不安があったが、これも予想を越えて楽しかった。ただ課題も見えたことも確かだった。どんなに良いライブでも課題が見えるライブというのもある。この日はそうだった。十分にエンジョイしたが、オレにはハッキリと越えるべき課題がみえた。
南相馬と新潟は素晴らしかった。特に新潟、10000人を前に純度の高い今のハイスタを見せられたと思う。アリーナも2本目ということもあってか要領を得始め、我ながら感動するような雰囲気の中でライブができた。ナンちゃんとも話してたのだが、朱鷺メッセではまた是非演りたい。
南相馬では新曲「Big Ol’ Clock」を初演した。これはこの場所で初演するんだと決めていた。
次の北海道の真駒内アリーナ、独特の温かい雰囲気の中でライブできた。すっかりアリーナでのライブにも慣れた。「なんだ、ハイスタってアリーナをライブハウスにできんじゃん!」とオレは思い始めた。
ただこの日、メンバーの体調が思わしくなく、少しだけ弱気になった部分が感じられた。3人ともこのツアーに賭けている。それぞれがどれだけ喜びと期待を持ちながら突入したか想像に難くない。体調を崩した本人が一番悔しいだろう。それはわかる。
ただ、観に来てくれた人にはそれでは済まない。なんの言い訳も効かない。オレはそこを一番重要視した。体調を崩したことなど責めたりする気持ちはこれっぽっちもない。ただステージ上では少しでも弱気になったら、それはダメだ。この日観に来てくれた方の中で「?」と感じた方はほぼいないとは思う。しかしオレは自分が感じたものを話し合いの土俵に乗せずにはいられなかった。この時、オレはこのツアーの強烈な牽引役になる決心をしたんだと思う。
翌日、札幌カウンターアクション。兄弟 KO の経営する名門ライブハウス。ハイスタは20年振りに兄弟がひたすら守ってきた場所に戻った。150人程度しか収容できない小さな箱。ハイスタはライブハウスから世の中に飛び出していった。皆さんがどういうイメージをお持ちかはわからないが……ハイスタというより、メンバー3人はそれぞれ未だにライブハウスの住人なのだ。それぞれの活動は今でもライブハウスを中心に行っている。ただハイスタとしてそこに戻れるのは非常に感慨深い。「Good Job Ryan! tour」でも宮古と石巻のライブハウスで演ったし、南相馬だってライブハウスだった。しかし札幌カウンターアクションに戻ることは……オレ個人的にだけかもしれないが、ちょっと意味合いが違った。
そのカウンターアクションの小さな汚い楽屋で、オレは昨日感じたことをメンバーに話した。オレが全て正しいとは思わない、しかしオレはこう思うと、真摯に話した。「そんなこと言われる筋合いはないと思われてもいい」、そう思いながら話した。しかしメンバーは真剣に受け止めてくれた。おそらくみんなが感じていたことをオレが議題にし、言語化しただけなのだろう。3人の気持ちはしっかりと同じ方向を向いていることを確認できた。
オレが思うに……この瞬間にハイスタはネクストレベルに上がったのではないか、と思う。
肝心のライブはというと、ステージを去ることが難しいほど素晴らしいものだった。「これだ!これなんだ!」と心の底から感じた。大事ではあるが楽しくもない話し合いをして、その後やったライブはたった150人の観客を前にバンドとして、ステージに上がる集団として、気持ちを一方向にまとめ、世界一のロックンロールを披露した。
あの晩のハイスタは世界一だった。他と比べようがないが、とにかく世界一のロックンロールバンドだった。
オレ達は兄弟が守ってきてくれたライブハウスで息を吹き返し、バンドを自分たちの手に確かに取り戻し、ネクストレベルに上がった。

「札幌カウンターアクションの楽屋にて。この日この場でオレ達は息を吹き返した。
ハイスタを自分達の手に確かに取り戻した瞬間の、なぜかの自撮り。」
オレはこのツアー中もリハーサルをしなかった。オレがライブ当日のリハーサルをしないのは Ken Band から一貫している。渋谷と名古屋はやった。それぞれツアー初日、アリーナの初日ということでやったが、それ以降はやらなかった。代わりにギターテックのミツルがやっていてくれたようだ(たまにヘイスミの猪狩が弾いてたらしく……ミツルとどっちが上か口論しているw)。めんどくさいからやらないのではなく、理由があってやらないのだ。メンバーもしょうがなくかもしれないが、理解してくれている。
その代わりに、出番前に必ず3人だけの時間を作るようにした。スタッフも全員部屋から退出してもらって一切入れない、3人だけで気持ちを確認する時間。そこでオレは毎日、「はいはい」と思われようが「もうわかったよ」と思われようがなんだろうが、自分が「闘将横山」になったつもりで、積極的にバンドに持つべき姿勢を言語化し、鼓舞した。そこで自分が発した言葉は、自分自身にも向けた。
特に札幌カウンターアクション以降は、これがとても肝になったんじゃないかと思う。わからない、オレだけかもしれないが、そう思う。
宮城以降アリーナ公演が続いたが、オレ達は毎晩のように世界一のロックンロールを鳴らした。やっぱり誰かの体調が思わしくない日もあった。オレなんかギターがめちゃめちゃ下手くそな日もあった。でももはやそれは関係なかった。
宮城、大阪2デイズ、福岡、熊本、下北沢、どれも素晴らしいライブだった。その晩しか起こり得ないケミストリーが存在したと思うし、事実オレは気分よかったし毎晩の出来事に満足だった。先述の朱鷺メッセだけではなく、またここでライブしたいと思うアリーナがいくつもできた。
お互いを鼓舞しあって、ハイスタを最大限にカッコよくする。
見に来てくれた方々の18年や20年の想いを真正面から受け止め、軽々とそれ以上のものを浴びせる。
「ハイスタって……なんであんなに凄いって言われてんの?」っていう素朴な疑問を持った新しい人達にも「なるほど、これはそう言われるわ」と思わせる。
世界一のロックンロールを鳴らす。
それしか考えてなかった。
どうすればその考えを達成できるか、オレはハッキリとわかっていた。
3人ともとんでもない力があるのだから、それを一つにまとめて、バンドとして同じ方向を向くことができれば、それは達成できるとハッキリわかっていた。
名前にぶら下がるなんてみっともないことはしない。
今回のツアーは自分達が心底そう思ってることを証明し、自分達自信も実感する最高の機会だった。
ハイスタだからすげぇんじゃなくて、すげぇからハイスタになったんだ。
始まる前は途方もなく長いものになる気がしたツアーも、あっという間にファイナルのさいたまスーパーアリーナの日を迎えた。
素晴らしい2時間半だった。長いツアーの疲労が蓄積されたのか、ナンちゃんの喉の調子がイマイチだった。でもナンちゃんはマイクにかじり付いて決して体が逃げてなかった。ハイスタのフロントマンを堂々と張ってみせた。
ツネちゃんは今までにない積極性を見せ、ライブ最大の見せ場をドラムソロで作り上げた。
最強のトライアングルだった。
ツアーが終わってしまうのが、ステージから去るのが寂しかった。演奏を終えて楽器を置いた後、最後にステージ上で3人で集まった。ナンちゃんはオレ達にだけ聞こえるように「あのマイクも……しばらく使わないと思うと寂しいね」と言った。もうすでにハイスタで歌うのを恋しがってる様子だった。
オレもやり切って誇らしい気持ちとともに、同じような気持ちを持っていた。

「ハイスタンダード @ さいたまスーパーアリーナ。このツアーは良くジャンプした。
そして飛び方や打点が20代の頃とほぼ変わっていないことに驚いた。
ってことは……70代になってもこうかなぁ?photo by teppei kishida」
「決め事」
ハイスタは世界一のロックンロールバンドだということをツアーを通して証明した。誰が認めなくても、オレはオレ自身に証明してみせた。
しかしそれは、さいたまスーパーアリーナまでの話だ。
これでいい気になっていたら、次はめちゃくちゃダサいことになるかもしれない。だから次に3人でステージ上に集まるなら、また気持ちを合わせるところから始める。
気持ちさえ合えば、自然と世界一のロックンロールが流れるはずなのだ。
来年はまたそれぞれの活動に戻る。
ハイスタとして次に何をするか、まだ話し合いは始まっていない。でもハイスタのことだから、また突然なにかをやるかもしれない。個人的には、せっかく良いアルバムを作ったので、もう少し何かしたい気もしているし。また3人で話していくが、現状特になにも決まっていない。次にいつどこで集まるかすら決まっていない。
ただ決まっていることは、ステージ上で再三再四発言してきたが「もうハイスタは二度と畳まない」ということ。
ペースはゆっくりになるだろうが、ハイスタは在り続ける。
毎年毎年なにかをやるようなバンドではないが、ハイスタは在り続ける。
来年に何か新しいアクションを起こすかもしれないし、もしかしたら3年後になるのか、10年後になるのか、それはわからない。
でも3人のうち誰かがおっ死ぬまで、ハイスタは畳まず、ハイスタとして在り続ける。
わかんない、そんなのはオレが言ってるだけかもしれない……突然ツネちゃんが辞めたいというかもしれない、ナンちゃんが辞めたいというかもしれない。
オレが辞めるかもしれない。
だから約束というわけではない。
でも、そう決まっている。
矛盾している、というか整合性がとれてないかもしれないが、そんなことはどうでもいい。
ハイスタは二度と畳まず、ハイスタとして在り続けると決まっている。
「最後に」
まず今回のツアーを支えてくれた周りのハイスタチーム、本当にありがとう。君たちのきめ細やかな動きなしでは、このツアーは気持ち良くできなかった。できたのは君たちのお陰です。音響、照明、ローディー楽器チーム、カメラマンクルー、Pizza Of Death、 HS、H.I.P.。ありがとう。引き続きよろしくお願い申し上げます。
現地のプロモーターの方々、いろいろなリクエストや急遽変更した部分にも迅速に対応していただいて、とても感謝しています。気持ち良くライブさせてもらいました。ありがとうございました。引き続きよろしくお願い申し上げます。
観に来ていただいた方々、激戦のチケットをゲットされて、万障繰り合わせの上お越しいただいてありがとうございます。皆さんの声援でバンドがノッて行った場面がいっぱいありました。やっぱりライブというものは、放つ側と受け止める側の両方で作り上がっていくものなんだなと改めて痛感しています。
万が一「90年代の方が良かった」とか「うーん、悪くはないけど大して響かなかったなぁ」という感想を持たれてしまっているようでしたら、非常に申し訳ありません。でもオレ達の力不足でしたとは言いません。毎晩、あれが精一杯でした。また観る機会があるようでしたら、その時はまた今回とも違ったハイスタをお見せできると思うので、是非いらっしゃってください。ありがとうございました。
一緒に出演してくれたバンド達、本当にありがとうございました。皆さんの存在と気迫にオレ達も火をつけられました。どのバンドもハイスタと一緒にライブすることを喜んでくれて、いかにハイスタに影響を受けたか公言してくれて、恐縮したけどすごく嬉しかったです。ナンちゃんが最終日のステージで「そういうバンド達が出てきてくれたというだけで、ハイスタでいて良かった」と言ってました。オレは皆さんのことを第一線で活躍するすごいバンド達だと思っています。ほとんどが後輩にあたる年代のバンド達ですが、後輩バンドだなどと余裕ぶっこいていません。幾つかのバンドは個人的にも尊敬しています。またどこかで一緒に演れる日を楽しみにしています。ありがとうございました。引き続きよろしくお願い申し上げます。
Ken Band、このツアーで得たものを持って帰るから、いろいろ覚悟しておいてねw 来年はやるぞ!
オレの音楽活動、プライベートを陰で支えてくれた友達、君らの存在がなかったら、君らがかけてくれた言葉がなかったら、こんなに強い気持ちでツアーにぶち当たれなかったよ。言葉では言い表せない気持ちだよ。
それから……ナンちゃん、ツネちゃん。別にこんなところで改めて言う必要もないけど、最高だったぜ!完全に「現在進行形のバンド」、しかも「世界一のロックンロールバンド」だったぜ、オレ達。なかなかこのツアーの思い出から抜け出せないね!でも得た手応えは次に活かそう。
しばらく離れた活動になるけど、なにか思いついたら……連絡ちょうだい。オレもするけど。
とにかく今年1年いろんな障害や壁を一緒に越えて、お互いを支え合ってやってこれたことに感動すらするよ。いろいろとありがとう。
オレと一緒にロックンロールしてくれてありがとう。
また近々ね。

「ツアー最終日のリハ後に全ツアークルーとともに記念撮影……したらしい。
オレはリハをしないので、映画『疾風勁草編」の時の等身大パネルで参加……したらしい。photo by teppei kishida」
2017.12.22